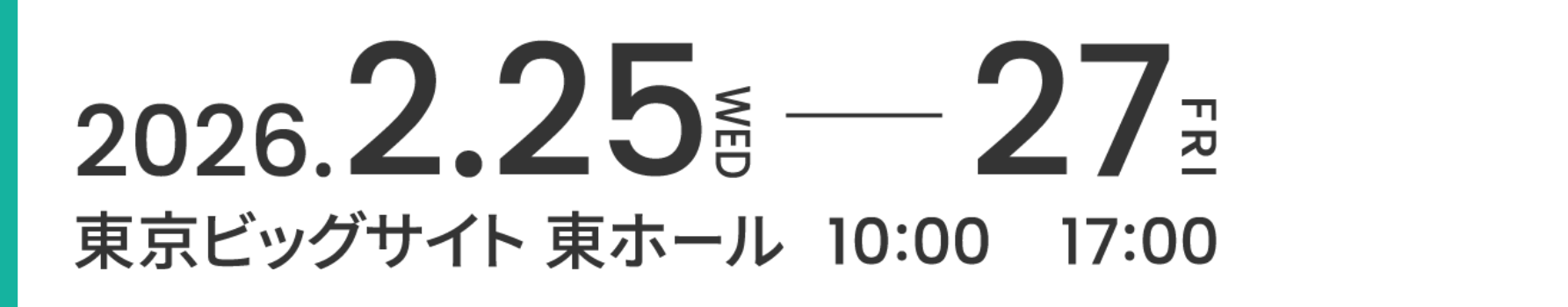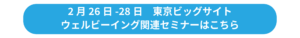ウェルビーイング プロジェクト
ウェルビーイングの取り組みを推進して豊かな社会を創造する
1947年に採択されたWHO憲章にて「健康」の定義の中でwell-beingという言葉が採用されました。
1980年代以降、米国の心理学者であるエド・ディーナーらによって「幸福度」「主観的ウェルビーイング」を測定する研究が始まり、以降、「ウェルビーイング」の定義づけとその達成に向け、何を指標においていくのかについての様々な研究、議論や実践が続いています。
また、ダボス会議・会長のクラウス・シュワブ氏は「グレート・リセット」を提唱し、経済システムや社会秩序を見直して刷新するべきだと指摘しています。今日では持続可能性や不平等の改善を目指す際に、既存の仕組みからなる社会構造自体を見直すことが求められているのです。
医学的ウェルビーイング
心身ともに病気ではない状態のこと。健康診断などの数値的な測定や、メンタルヘルスについて質問表によるチェックなどで測るもので、これまで長い間研究がなされ、私たちの意識や暮らしの中にも浸透しています。
快楽的ウェルビーイング
一方、医学的な側面だけでは測れない、「個人が幸福や生活への満足度をどう捉えているか」についてを、前述の「主観的ウェルビーイング」で測っていきます。エド・ディーナー氏が開発した「人生満足度尺度」では、以下の5つの質問について「まったく当てはまらない」から「非常に当てはまる」まで、1点〜7点の点数を「自己報告」させることで、個人の満足度を測ります。
国連が2012年以降、「国際幸福デー」に毎年発表している「世界幸福度調査」の設問においても、主観的ウェルビーイングとして「生活評価」と「ポジティブ感情」「ネガティブ感情」が尺度として用いられています。
持続的ウェルビーイング
近年「ウェルビーイング」と言われる際にメインとなるのが、この持続的ウェルビーイングです。
各人が、その心身の「潜在能力」を発揮したり「人生の意義を発見」すること、「自己決定権」を持っていることなど、持続的・包括的な豊かさをとらえる指標です。その状態は、「フラリッシング(flourishing)=開花」と表現され、日本語では「持続的幸福感」「いきいきとした状態」と訳されることもあります。
ポジティブ心理学の提唱者であるマーティン・セリングマン氏は2011年に発表したPERMA理論で、以下の5つを指標としています:
・P : Positive Emotion(ポジティブな感情)
・E : Engagement(エンゲージメント、没頭)
・R : Relationships(ポジティブな関係性、人間関係)
・M : Meaning and Purpose(人生の意味や目的)
・A : Accomplishment(達成感)
これら1〜3の考え方をベースにして組み合わせながら、人々が一生を過ごしていく中で、肉体的・精神的・社会的に「いきいきとした状態」が続いていくことを目指す、そのための指標づくりや測定、また改善や実現に向けた取り組みが、世界的に行われるようになってきているのです。
特に健康分野において創刊から50年以上の歴史を持つメディアや1980年頃から次々に立ち上げたイベント、コミュニティを活用して、啓発活動を行い、社会全体へと取り組みを広めていくことを目指しています。
アーカイブ配信中【配信期間:2月10日~4月30日】 ※2025年1月17日開催
後援団体(2025年1月17日開催のカンファレンス)
 |
協賛メディア(2025年1月17日開催のカンファレンス)
 |  | |
 |  |
お問い合わせ先
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
Email: promotion@healthcarejapan.com TEL: 03-5296-1020